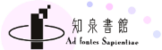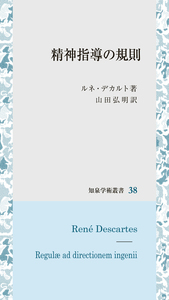ホーム > 精神指導の規則
目次
はじめに
凡例
精神指導の規則
規則 I
規則 II
規則 III
規則 IV
規則 V
規則 VI
規則 VII
規則 VIII
規則 IX
規則 X
規則 XI
規則 XII
規則 XIII
規則 XIV
規則 XV
規則 XVI
規則 XVII
規則 XVIII
規則 XIX
規則 XX
規則 XXI
付録
デカルト『方法序説』第二部(1637)
『べークマンの日記』(1628–1629)
アルノー/ニコル『ポール・ロワイヤル論理学』第2版(1664)
ポワソン『デカルト『方法序説』注解』(1670)
バイエ『デカルト氏の生涯』(1691)
『学芸雑誌』(1703)
訳者解説
主要文献
訳者あとがき
索引
凡例
精神指導の規則
規則 I
規則 II
規則 III
規則 IV
規則 V
規則 VI
規則 VII
規則 VIII
規則 IX
規則 X
規則 XI
規則 XII
規則 XIII
規則 XIV
規則 XV
規則 XVI
規則 XVII
規則 XVIII
規則 XIX
規則 XX
規則 XXI
付録
デカルト『方法序説』第二部(1637)
『べークマンの日記』(1628–1629)
アルノー/ニコル『ポール・ロワイヤル論理学』第2版(1664)
ポワソン『デカルト『方法序説』注解』(1670)
バイエ『デカルト氏の生涯』(1691)
『学芸雑誌』(1703)
訳者解説
主要文献
訳者あとがき
索引
内容説明
学院の卒業後に兵役やヨーロッパ遍歴をへた若きデカルトが,それまでに行なってきた数学や自然学の研究を踏まえ,自身の学問観とその方法論をまとめたのが,『精神指導の規則』(『規則論』1628?)である。
未完・未刊行ながらデカルトの死後その遺稿『規則論』は『ポール・ロワイヤル論理学』やライプニッツなど哲学・科学に大きな影響をあたえたことで知られている。
「研究の目的は,現れてくるすべてのものについて確固とした真なる判断を下せるよう,精神(ingenium)を導くことでなければならない」という規則Ⅰからはじまり,「事物の真理を探究するには方法が必要である」(規則IV)など21の規則とその説明が並ぶ。すべての人間にそなわっているが未完成の状態の精神を,直観・演繹・枚挙を核とした数学をモデルとした真理探求の方法・規則といった思考の技法によって導く。
本書は,原本が失われている『規則論』の現存する複数の写本を参照のうえ翻訳,さらに各規則間の関連や,『方法序説』(1637),『省察』(1641)などその後のデカルトの著作への発展に関する注も充実している。また付録として『規則論』がデカルトの死後どのように伝承され,影響をあたえたのかを知るためのテキストも収録。本書はまさにデカルト哲学の「原基」である『規則論』の決定版。
未完・未刊行ながらデカルトの死後その遺稿『規則論』は『ポール・ロワイヤル論理学』やライプニッツなど哲学・科学に大きな影響をあたえたことで知られている。
「研究の目的は,現れてくるすべてのものについて確固とした真なる判断を下せるよう,精神(ingenium)を導くことでなければならない」という規則Ⅰからはじまり,「事物の真理を探究するには方法が必要である」(規則IV)など21の規則とその説明が並ぶ。すべての人間にそなわっているが未完成の状態の精神を,直観・演繹・枚挙を核とした数学をモデルとした真理探求の方法・規則といった思考の技法によって導く。
本書は,原本が失われている『規則論』の現存する複数の写本を参照のうえ翻訳,さらに各規則間の関連や,『方法序説』(1637),『省察』(1641)などその後のデカルトの著作への発展に関する注も充実している。また付録として『規則論』がデカルトの死後どのように伝承され,影響をあたえたのかを知るためのテキストも収録。本書はまさにデカルト哲学の「原基」である『規則論』の決定版。