
ホーム > ルネサンス教育論集

知泉学術叢書39
| 著者 | レオナルド・ブルーニ 著 エネーア・ピエール・パオロ・ヴェルジェリオ 著 シルヴィオ・ピッコローミニ 著 バッティスタ・グアリーノ 著 加藤 守通 訳 伊藤 博明 訳 坂本 雅彦 訳 |
|---|---|
| ジャンル | 教育学 |
| シリーズ | 知泉学術叢書 |
| 出版年月日 | 2025/08/25 |
| ISBN | 9784862854414 |
| 判型・ページ数 | 新書・420ページ |
| 定価 | 本体5,000円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
目次
1 レオナルド・ブルーニ 教養書簡集
解説
翻訳
1 ニッコロ・ニッコリ宛――ラチェニーゴ,1400年9月5日
2 ポッジョ・ブラッチョリーニ宛――フィレンツェ,1416年9月13日
3 ジャンニコラ・サレルノ宛――フィレンツェ,1418年後半
4 デメトリオ宛――フィレンツェ,1424-26年
5 トンマーゾ・カンビアトーレ宛――フィレンツェ,1420-28年
6 ニッコロ・ストロッツィ宛――フィレンツェ,1431-34年
7 フラヴィオ・ビオンド宛――フィレンツェ,1435年5月7日
8 カスティリア王フアン2世宛――フィレンツェ,1436年
9 ミラノ大司教フランチェスコ・ピッコルパッシ宛――フィレンツェ,1440年前半
10 ラウロ・クィリーニ宛――フィレンツェ,1441年
11 ジョヴァンニ・チリニャーニ宛――フィレンツェ,1442年9月12日
2 ピエール・パオロ・ヴェルジェリオ 自由な青少年にふさわしい性格と学問についての本
解説
翻訳
両親の義務
自由学芸の重要性
優れた素質について
若者の性格
国家による教育への関与
性愛への警戒
教師の選択
飲酒への警告
宗教教育
年長者への敬意
良き助言者の必要性
過保護に対する警告
自由学芸の意義
幼少期から学ぶべき
生涯を通して学ぶべき
飴と鞭
武芸と文芸
文芸の効用
書物の効用
道徳哲学と歴史
絵画
文芸――弁証法・弁論術
詩学
算術・幾何学・天文学
医学・法学・神学
自分に適した学問に取り組む
才能の種類
最良の教師から最良の著作を学ぶべき
学習のヒント――乱読の戒め
毎晩の復習
不断の学習
体育と軍事教練
ウベルティーノへの賛辞
スパルタとローマ
文芸と体育――時間の配分
体育における配慮
余暇の過ごし方
身だしなみ
結語
3 レオナルド・ブルーニ 学問と文才について
解説
翻訳
はじめに――才能を完成へ!
文才を磨くために(その1)――注意深い読書
文才を磨くために(その2)――語りのリズムをつかむ
学問的知識について(その1)――深入りしないほうがよい学問
学問的知識について(その2)――キリスト教と道徳哲学
学問的知識について(その3)――歴史と弁論術
学問的知識について(その4)――詩学
詩に対する賛美と擁護
おわりに――事物の知識と熟達した文才
4 エネア・シルヴィア・ピッコローミニ 子どもの教育について
解説
翻訳
序言――ラディスラウス殿下へ
殿下における美徳の獲得
教育の重要性
教師の役割
身体の訓練と遊び
食物と飲料
節度ある食事
適度な飲酒
身体の配慮
精神の教育
王の義務
文学の意義
王子の心得
演説の力
演説の訓練
記憶力の鍛錬と文法
自国語と単純語
本義語と転義語
常用語と新造語
縮小語,変化形,派生語
不純語法と文法の違反
推論と語源
言葉の権威
慣用の重要性
詩人について
神学者について
詩人の選別
詩人の効用
歴史家の効用
正書法
前置詞と合成語
子音の重複
子音の消失,無変化,変化
帯気音化
弁論術と弁証学
音楽の効用
幾何学と天文学
多くの学芸の習得
道徳哲学の意義
5 バッティスタ・グアリーノ 教授と学習の順序について
解説
翻訳
序文――マッフェオ・ガンバラへの献辞
父の理論を踏襲
学習意欲が重要
教師の選択
体罰批判
学友との競争
初学者の教育――発音と文法
文法
音節
ギリシア語を学ぶべき
ギリシア語文法の学習
ギリシア語での読書の順序
繰り返し書く
ラテン語の更なる学習
歴史の学習
詩の学習
修辞学
道徳哲学
学んだことを教える
独学の重要性
抜粋の効用
ギリシア語上達の極意
音読のすすめ
読書のコツ
時間配分
文学の学習の魅力
時間を大切にする
結語
解説
1 近代教育論の源流
2 ブックハンターたち
3 ペトラルカの功績
4 人文主義とは何か
5 ギリシア語学習の時代
6 引用の共同体
7 本書の構成
あとがき
索引
解説
翻訳
1 ニッコロ・ニッコリ宛――ラチェニーゴ,1400年9月5日
2 ポッジョ・ブラッチョリーニ宛――フィレンツェ,1416年9月13日
3 ジャンニコラ・サレルノ宛――フィレンツェ,1418年後半
4 デメトリオ宛――フィレンツェ,1424-26年
5 トンマーゾ・カンビアトーレ宛――フィレンツェ,1420-28年
6 ニッコロ・ストロッツィ宛――フィレンツェ,1431-34年
7 フラヴィオ・ビオンド宛――フィレンツェ,1435年5月7日
8 カスティリア王フアン2世宛――フィレンツェ,1436年
9 ミラノ大司教フランチェスコ・ピッコルパッシ宛――フィレンツェ,1440年前半
10 ラウロ・クィリーニ宛――フィレンツェ,1441年
11 ジョヴァンニ・チリニャーニ宛――フィレンツェ,1442年9月12日
2 ピエール・パオロ・ヴェルジェリオ 自由な青少年にふさわしい性格と学問についての本
解説
翻訳
両親の義務
自由学芸の重要性
優れた素質について
若者の性格
国家による教育への関与
性愛への警戒
教師の選択
飲酒への警告
宗教教育
年長者への敬意
良き助言者の必要性
過保護に対する警告
自由学芸の意義
幼少期から学ぶべき
生涯を通して学ぶべき
飴と鞭
武芸と文芸
文芸の効用
書物の効用
道徳哲学と歴史
絵画
文芸――弁証法・弁論術
詩学
算術・幾何学・天文学
医学・法学・神学
自分に適した学問に取り組む
才能の種類
最良の教師から最良の著作を学ぶべき
学習のヒント――乱読の戒め
毎晩の復習
不断の学習
体育と軍事教練
ウベルティーノへの賛辞
スパルタとローマ
文芸と体育――時間の配分
体育における配慮
余暇の過ごし方
身だしなみ
結語
3 レオナルド・ブルーニ 学問と文才について
解説
翻訳
はじめに――才能を完成へ!
文才を磨くために(その1)――注意深い読書
文才を磨くために(その2)――語りのリズムをつかむ
学問的知識について(その1)――深入りしないほうがよい学問
学問的知識について(その2)――キリスト教と道徳哲学
学問的知識について(その3)――歴史と弁論術
学問的知識について(その4)――詩学
詩に対する賛美と擁護
おわりに――事物の知識と熟達した文才
4 エネア・シルヴィア・ピッコローミニ 子どもの教育について
解説
翻訳
序言――ラディスラウス殿下へ
殿下における美徳の獲得
教育の重要性
教師の役割
身体の訓練と遊び
食物と飲料
節度ある食事
適度な飲酒
身体の配慮
精神の教育
王の義務
文学の意義
王子の心得
演説の力
演説の訓練
記憶力の鍛錬と文法
自国語と単純語
本義語と転義語
常用語と新造語
縮小語,変化形,派生語
不純語法と文法の違反
推論と語源
言葉の権威
慣用の重要性
詩人について
神学者について
詩人の選別
詩人の効用
歴史家の効用
正書法
前置詞と合成語
子音の重複
子音の消失,無変化,変化
帯気音化
弁論術と弁証学
音楽の効用
幾何学と天文学
多くの学芸の習得
道徳哲学の意義
5 バッティスタ・グアリーノ 教授と学習の順序について
解説
翻訳
序文――マッフェオ・ガンバラへの献辞
父の理論を踏襲
学習意欲が重要
教師の選択
体罰批判
学友との競争
初学者の教育――発音と文法
文法
音節
ギリシア語を学ぶべき
ギリシア語文法の学習
ギリシア語での読書の順序
繰り返し書く
ラテン語の更なる学習
歴史の学習
詩の学習
修辞学
道徳哲学
学んだことを教える
独学の重要性
抜粋の効用
ギリシア語上達の極意
音読のすすめ
読書のコツ
時間配分
文学の学習の魅力
時間を大切にする
結語
解説
1 近代教育論の源流
2 ブックハンターたち
3 ペトラルカの功績
4 人文主義とは何か
5 ギリシア語学習の時代
6 引用の共同体
7 本書の構成
あとがき
索引
内容説明
15世紀初頭の北イタリアでは,人文主義の勃興とともに新しい教育機関が設けられ,教育論・学習論が次々と執筆された。本書は,代表的な4人の思想家の著作と書簡を詳細な注と解説を加えて訳出する。近代教育の基盤とも言えるルネサンスの教育思想および理想的人間像とは,どのようなものであったのか。
初期ヒューマニズム最大の理論家の一人ヴェルジェリオによる『自由な青少年にふさわしい性格と学問についての本』(1402頃)は,自由学芸を初めて体系的に論じ,エラスムスが登場するまで最も読まれた教育論であった。
フィレンツェの書記官長で多彩に活躍したブルーニは,新発見のキケロ『弁論家について』に影響を受け,真の学識は知識とレトリックが一体化した境地にあるとして『学問と文才について』(1422-29頃)を著した。彼の膨大な書簡から抜粋した「教養書簡集」(1400-42)には,同時代の人文主義サークルの知的動向が如実に窺われる。
後年,教皇に即位したピッコローミニの『子どもの教育について』(1450)は,統治者以上に智恵を必要とする者はいないと論じ,幼少のハンガリー王のために身体と精神の鍛練を考察した上で,宗教的な教育,そして読書と学習のプログラムを取り扱う。
グアリーノ『教授と学習の順序について』(1459)は教育者の父が創設した学校の実践と理念を克明に描き,ドイツのギムナジウムやフランスのリセの原型となった。
現代における子どもの教育のみならず,読書論や独学にも豊かな示唆を与える,西洋教育思想史の古典論集である。
初期ヒューマニズム最大の理論家の一人ヴェルジェリオによる『自由な青少年にふさわしい性格と学問についての本』(1402頃)は,自由学芸を初めて体系的に論じ,エラスムスが登場するまで最も読まれた教育論であった。
フィレンツェの書記官長で多彩に活躍したブルーニは,新発見のキケロ『弁論家について』に影響を受け,真の学識は知識とレトリックが一体化した境地にあるとして『学問と文才について』(1422-29頃)を著した。彼の膨大な書簡から抜粋した「教養書簡集」(1400-42)には,同時代の人文主義サークルの知的動向が如実に窺われる。
後年,教皇に即位したピッコローミニの『子どもの教育について』(1450)は,統治者以上に智恵を必要とする者はいないと論じ,幼少のハンガリー王のために身体と精神の鍛練を考察した上で,宗教的な教育,そして読書と学習のプログラムを取り扱う。
グアリーノ『教授と学習の順序について』(1459)は教育者の父が創設した学校の実践と理念を克明に描き,ドイツのギムナジウムやフランスのリセの原型となった。
現代における子どもの教育のみならず,読書論や独学にも豊かな示唆を与える,西洋教育思想史の古典論集である。
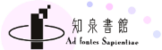





![名婦伝[ラテン語原文付]](..//images/book/638314_sml.jpg)










